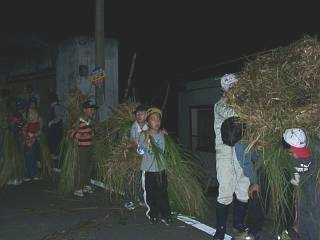坊津町十五夜行事 (bounotu jyugoya)
坊津町 ぼうのつ
南薩摩の十五夜行事は、国の重要無形民俗文化財に指定されています。坊津には
独特の十五夜行事が保存、継承されて、集落毎に、それぞれ違った風変わりな伝承が
残っています。代表的なものには、5つのパターンが見られるようです。農村型ー栗野
清原地区。漁村「浜」型ー坊、久志地区。特殊型ー上之坊、鳥越地区。泊型。秋目型
十五夜の行事共通は、縁側や庭先に臼を出し、箕・みを置き、一升枡等に里芋・唐芋
お団子など、ススキや秋の草花を飾りお供えします。綱引きと相撲は南薩摩に限らず
薩摩全般で行われている、定番の十五夜行事です。土俵や綱引きに使う綱は、山や
原野から、茅やかずら、竹などを取ってきて「茅刈る・茅引き」、それで綱を練ります。
 |
泊集落では、十五夜の約2週間前から、まず八朔の日にすじまわりをして、十五夜行事のあることを町内に知らせて歩きます。
この集落では、女子による十五夜踊りがあります。また、その踊りに飛びこんで、踊りの輪を崩す踊りこわしも。以前は踊りも踊りこわしも、14日と15日にあったそうですが、現在は15日だけ。十五夜の午後3時頃から、公民館ー九玉神社まで踊りながら宮参りをし、境内でも、踊りを奉納します。暗くなってから、着物から浴衣に着替えて、広場で十五夜踊りを踊ります。この時男子が輪の中に飛びこみ、ワルさや、踊りの輪を駆け抜けます。少年少女だけになって、以前のように、気のある人に抱きついたり手を握ったりはなく、せいぜい踊りの小道具を持って行ったりするくらい。無礼講の男女交際認可のチャンスだったのでしょう。 |
 |
 |
左 すじまわり。筋廻り・辻廻り。男の子が地域の地名・十五夜等の書かれた灯篭を持って、大声で唄い和し、集落に行事のあるのをふれ回る。
右 すじ廻りの後、夜相撲。土俵は前日に弘法の井戸の横の広場に作る。 |
| 上3枚、右写真は宮参り行列。十五夜の昼間、公民館から九玉神社まで行進。16歳までの女子は、着物で白鉢巻に扇子とシベを持つ。男児は鉢巻、およびシベ傘を被る。踊りの女子、男児、青年団の順に行列。このとき、踊りの歌のうしろは、「おくめくどき」「十五夜唄」など唄いながら、神社に向う。神社では、神事のあと、十五夜踊りを奉納して解散。帰りは前もって奉納していた柱「帆柱」を青年団旗、男児、踊りの順で戻るそうだが、見ていると踊りはそれぞれ三々五々、自宅に向った様子。3時から2時間かからず終了。女子は浴衣に着替え7時頃、男子は夕方6.30からのすじまわりまで休憩。 |
 |
暗くなる6.30頃から男子はすじまわりに出かけ、女子は7.00頃から浴衣で十五夜踊りをはじめる。興も乗った頃、すじまわりから帰ってきた男児たちは、石油缶を叩きながら、この踊りの輪の中に突っ込む。何度も行うようだが、この年は3回であっという間の出来事だった。デジカメでは、押えきれなかった。踊りも壊れない・・その後、ハンヤ踊りなどもあり、一般の人も参加。その間に女子は洋服に着替え、通りを飾っていた綱を外し、綱引きをする。集落の真中から九玉神社側と寺「本珠院」側。男対女。大人対子供等に分かれて、道路「国道226号線」で。
綱引きの終わった綱は、一度公民館のすじに引きずって入れて、また元に戻し、竜の尻尾の方と見たてた数mを切って、横の泊川に投げ入れる。綱引きのアトからの行為は「綱引きずり」と言われる。 |
泊十五夜唄 すじまわりの唄
1.沖の双子瀬が手を組んだ裏に大漁の声がする
2.水は流れる泊川いつもきれいにさらさらと
7.宮ん崎から沖見れば 景色の良さは日本一
8.泊の子どんは良か子どん あまって遊んで勉強する
10.十五夜様にダゴあげて おどいも踊って宮参り
12.泊の姉さんたちゃ愛きょ良し色は黒いが良かおなご
ヨオーイ ヨオーイ ヨォイヤナ ハーレヤナ ヤートォコセ
泊の浜の青年よ盛んにやれよ十五夜を サゴエーイエーイ |
泊十五夜唄 おくめくどっ「お久米 口説き」
宮参りの行列行進の際等に唄う。
十五夜踊り
1.しべ踊り
そんが節
志布志千軒
2.扇子踊り
おそめ
四節節「しせっぶし」
3.手踊り
潮来出島
|
 |
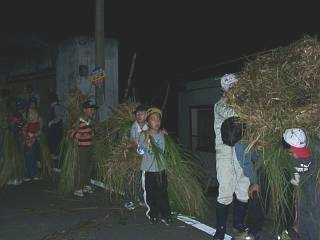 |
火とぼし 火点し
茅引きした茅で番茅を作り、その夜は途中の整列位置に運び下げ、上道の坂の中間点でひとぼしをする。これは、番茅を担ぐ中学生以上の青年。それ以下は火消し役。下に見える集落に、出来あがった合図を松明をくるくる回し、その後大声でも、下に知らせる。
|
火とぼしあと、番茅を帰路の整列から運ぶ。重量が100キロを超えるので、地域の全員で手分けして運ぶ。公民館の庭までの間、青年が口説き、子供はハヤシをする。公民館入口で止まって、名前を名乗ったのち、運び込む。 |
 |
上之坊の十五夜行事は、火とぼしだけが有名になり、ほかの行事はあまり知られていません。ほかの集落と同じような口説き唄やハヤシ、茅引き、綱ねり、相撲、綱引きもあり、これ以外にも、ここだけの、ほかの変わった行事が残っています。いずれ取材してみたいと思います。 左写真は上坂の中間点・火とぼしの場所から上之坊集落を見下ろす。日が落ち、V字になった集落の明かりと、右山の上の灯台の明かりが・この直後火とぼしがスタート。 |
鳥越の十五夜行事も、風変わりな行事が伝承されています。おもなものが、ふたつあり
ひとつは、「手つなっご」です。これは茅引きの最終日に行われ、男子のふんどし姿が
火とぼしの火に照らされ、勇壮かつユーモラスでもあり、満月の晩の幻想でもあります。
もうひとつが、手つなっごが済んだアト、行われる「どんとせ」です。現在は小学校正門
前で行われ、石階段に並んで見物できます。おしくらまんじゅう十五夜版でしょうか。
 |
 |
| 茅引きのあと松明持ち一人と、嫁女かつぎの先発隊が3組、時間を置いて、見せ場「集落の1キロ手前の川べりに到着。対岸や近くには見物人、カメラマンが待機。本隊の各人の松明も路肩の数ヶ所でまとめて燃やす。そこで口説きに合わせて十五夜唄を斉唱する。17−18歳は手をつないで左右に走る。唄の途中で真中で手を切り、左右に別れる。また手をつないで、7-8回繰り返す。 |
手つなっごが終わったら、公民館の庭まで茅を運んで積む。その後、行列を組んで十五夜唄を唄いながら小学校正門前に。どんとせのハヤシで青年は前に距離を離す。また、どんとせのハヤシで見物人の前まで、うしろ向きで戻り、ヤッホヤッホの掛け声で残っている青年とおしくら饅頭をする。また、前に行き、後向きに引き返す。時々フェイントで外し、見物人から笑いが出る。 |
 |
 |
左、ヘゴと茅で作られた嫁女・よめじょと呼ばれる。17−18歳が作る。茅引きの時、他の茅と一緒に公民館まで降ろす。
右 手つなっごを前から撮る。火とぼしの明かりで、幻想的。 |
行事場所の詳細地図=リンク ヤフー・マッピオン
 |
 |
 |
| 坊の一番奥 坊之浜集落の綱 |
同じ太さでない |
下浜集落の綱 |
夜の綱引きのため、各集落の道路脇に寄せてある。車で1分もかからない歩いても数分で行ける
それぞれ集落が近い。それでも、別々の地域で別の綱で、綱引きをする。
長い間、先人から受け継がれてきた十五夜行事は、まだなんとか形になって残っているが、
少子化や、青年層の都会流失により、行事の簡素化や、行事の中止部分も出て来ているし
行事の変化のあるのも、紛れのない事実のようです。以前はもっと賑やかだった、人が少ないね
などの声もよく耳にしました。これも、時代の流れで、仕方がないと言えば言えますが・・・・
それでも、集落毎に公民館活動を通じて、伝承努力している有志の方々もおいでになるそうです。
この、坊津の十五夜行事、ほかの伝統祭りも、いつまでも引き継がれてゆくように祈念します。
取材・2004 9・14/19/24/25/28
坊津町史談会会員 輝津館館長 早水廣雄様から頂いた資料による ・
表紙 次頁30