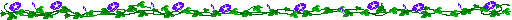会長 池田琢哉
副会長 太原博史
理事 河野嘉文、吉永正夫、川上 清、武井修治
児玉昭彦、川畑清春、江口 智、村上直樹
中園伸一、 南 武嗣、 鬼丸高恒、太原博史
監事 藤田虎夫、鉾之原 昌
顧問 西 健一郎 、鮫島信一
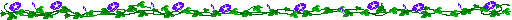
少子化防止で日本を救おう
鹿児島県小児科医会顧問 鮫島信一
1.はじめに
わが国では少子高齢化が急速に進んでいます。長寿は歓迎できますが、少子化は日本丸沈没の危険性をはらんでいます。政府やマスコミもやっとそのことに気付いて騒いでおりますが、対応は遅々として進まず、少子化問題はいよいよ難題になってしまいました。
少子化防止、子育て支援について思うことを述べてみました。ご批判やご意見を頂ければ幸甚です。
2.日本の財政事情
内閣府や財務省の資料によると、平成11年度の日本国民の年間総所得は、およそ380兆円。平成15年度の国家予算は82兆円規模なのに、国の借金は850兆円を超えており、国家予算の10倍以上の借金です。一方日本人は節約を美徳として、使わないお金は預貯金にまわすという高度な経済感覚を持っています。そのようにして蓄えた金融資産が1400兆円と試算されています。これは銀行などの預金や生命保険、株式、債券等すべてを含んだ金融資産の総額であり、昭和62年のバブル経済の絶頂期には、アメリカを抜いて日本が世界一の債権国となりました。何でも世界一でありたいアメリカが悔しがったのは当然です。そして日本バッシングが始まりました。為替が円高に誘導され、日本の輸出製品が売れなくなり、バブル経済後の日本丸浸水が始まったのです。
日本国家の多額の債務は、外国からの借金では無く、国債など日本国民からの借金が大部分であるということで、政治家も官僚もこの借金を殆ど心配していないように思います(裏では、通貨切り下げや強烈なインフレ策が準備されているのかも知れません?)。
納税者である国民は、「税金は高い」、「消費税値上げ反対」を叫んでいます。しかも経済は不況で、活性化の為には公定歩合の引き上げはできず、超低金利政策は続けざるをえません。これらを勘案すれば、さらなる増税は無理です。税収が不足すれば、手がけ易い医療・保健・福祉予算の削減が登場してきます。海外援助資金や防衛予算の削減等を求める意見もありますが、立場が違えば反論もあり、既に約束された予算の削減は難題です。小泉内閣は聖域無き構造改革を旗印に頑張っていますが、目標として掲げた80兆円以内に国家予算は減らせませんでした。
歳出減が期待できなければ、歳入増を計らねばなりませんが、個人一人当たりの労働生産性の向上にも限度があり、歳入増への切り札は、労働人口の増加しかないように思います。そのためには、今のいびつなひょうたん型の人口構成から、理想的なピラミッド型の人口構成へ移行する必要があり、少子化防止、子育て支援策を国家的緊急の課題として取り組むことが必要です。
3.少子化とリストラ
厚労省の統計資料によると、昭和25年(1950年)には1年間に230万人の赤ちゃんが生まれました。50年後の平成12年(2000年)には119万人と半減しました。50年後の平成62年(2050年)にはその半分の60万人になるとの予測があり、生まれる子どもの数がこのまま減少すれば国家存亡の危険性があります。
少子化傾向に対し、「狭い日本に人口が多すぎる、自然が与えた絶好のリストラだ」として容認する意見もありますが、国家財政の収支のバランスが崩れて、850兆円もの負債を抱えての現状では、労働人口が減るようなリストラはできないと思います。人手不足に対し、外国人労働者を雇うという考え方は、既にヨーロッパで、社会不安や差別などの政治社会問題となり、失敗しました。単一民族を自慢している今の日本には無理な政策です。
4.少子化の影響
子どもが少なくなれば、次世代を荷う生産人口が少なくなるわけで、既に農業、林業、水産業等の一次産業は後継者がいなくて困っております。更に人手を要する仕事への就職は敬遠され、自由な職業選択もできなくなります。子どもたちにとっても、子どもの過疎化が起こり、子どもと遊ぶ相手は同年代の子どもではなく、親であり、大人や老人になるという困った現象が起こります。
少子化の原因には、子育て費用の増大、住宅事情、核家族化、女性の職場進出、晩婚、子育て意識の変化などいろいろな要因が複雑微妙に絡んでの結果でありますが、赤ちゃんを産むのに、人に頼まれたり社会の為に産んだりするわけではありません。しかし、子どもは成人して一人前の社会人になれば、納税者となり社会に大きく長く貢献することになるし、親に尽くすより、遥かに大きく社会の為に尽くすようになるのです。まさに「子は人の子、社会の子」なのです。
このように大切な社会の宝を一人前に育てるには、少なくとも20年の歳月を要します。しかも教育費、医療費、生活費等の子育て費用が高くつくのも事実です。その間の育児支援のために、親個人だけでなく社会全体もまた大幅な援助をすべきです。
5.子育て支援
2〜30年前は長男の嫁探しに苦労しました。嫁が親(老人)の面倒をみなければならなかったからです。その後、年金を始め各種の老人福祉政策が功を奏して、老人は胸をはって生活できるようになり、日本は世界一の長寿国になりました。同じ様な優遇策を子育て中の若者向けに実行すれば、少子化防止策になると思います。「子どもを産みたい、産んでもよい」と考えている人が「子育てにはお金がかかる、子育ては難儀だ」などと経済的、社会的支援不足のために、子育てを諦める事があっては、その人ばかりでなく社会全体にとっても悲しい残念な出来事です。
子育ての苦労をしないで、豊かな生活を楽しんで居られる方々には、応分の子育て支援(税金などで)をお願いしたら如何でしょうか。産みたくても産めない方々もあり、社会の親として支援することになれば、人の親としての社会的責務を果たすことになり、相応の満足感が味わえるのではないでしょうか。
6.心の健康
人間の健康とは、身体的、精神的健康が言われておりますが、更に社会的健康を加えた3本の柱が必要です。このどれかが欠けても健康とは言えません。テロリストは、神の使者を認んじていても、人の命の尊さを軽んじているので社会的健康はありません。
子どもによる極悪な犯罪が報道されることがありますが、しつけや社会的健康教育は幼児期から必要で、何でも欲しいままに与えるのではなく、善悪の判断や耐える心を培うことは極めて大事です。育児に際しては、この3本の柱の育成に十分気配りをして欲しいと願っています。
子育てに際して、自分の生活や都合を優先し、子どもの成育に無頓着な親がいるのも事実です。子どもは日々成長、発達するのが特徴です。心身の発育には、常に気をつけて観察する必要があり、心の乱れや悩みが不登校の原因となり、犯罪に繋がり易いので、親子の絆はしっかりと育むことが大事で、早期発見、きめこまかな早期治療が必要です。親子離反は少子化より質が悪いと認識して下さい。
7.子育て支援対策
子どもは両親によって家庭で育てるのが理想ではありますが、家族や周囲の協力が無くてはうまく行きません。それは専業主婦でも、共働きの場合でも同じことです。
女性の職場進出と少子化は密接に絡んでおりますので、女性の働きやすい環境作りも緊急の課題です。母子保健法を配慮した企業の雇用条件の改善や保育施設の機能拡大など育児支援制度の充実が大事で、保育所同士の横の繋がりや病児保育などの子育て支援網を広げて、育児と仕事の両立が出来る環境作りが必要です。
子育て奮闘中の専業主婦には社会的サービスがほとんど無く、24時間休みのない育児に心身ともに疲れきった状況に放置されています。一人になれる時間がない、話す相手がいない、社会から取り残されるような焦りがある、子どもに何かあったら全部母親の責任といわれる、しかも経済的支援は何も無いなどと育児を荷う心身の負担が重くのしかかっているのです。
乗り物や買い物をしている妊婦には優しく労り、赤ちゃん抱っこの母親や子ども連れの家族に対しては親しく励ましの声援をおくるなどの気配りをして、親個人だけでなく、社会全体で子育てを支援しているのだと言ったそんな雰囲気が大事です。
わが国では古く万葉の時代に、山上憶良は「白金も 黄金も玉も 何せんに まされる宝 子にしかめやも」と詠んで、これまでいつの時代でも子どもは大切に育てられてきました。交通機関の乗車券や施設入場料も子どもは半額と優遇されてきたのです。ところが医療保険では今回の改訂でやっと3歳未満児の2割負担という優遇策が登場してきました。今後は15歳までの1割負担へと拡大して欲しいと思います。このような小さな支援策や気遣いが一時的でなく、継続して、次々に示されれば子育てムードが変わります。子育て環境が良くなれば、少子化防止は目に見えて明るくなります。
8.経済効果
赤ちゃん一人を20歳まで育てるのに要する費用は、約3千万円と試算されています。出生数が1割(10万人)増えると3兆円の消費が増える事になります。10年続ければ30兆円の消費増となる訳です。更に財布の紐の硬い老人も孫可愛さ故に各種のプレゼントやカメラ、ビデオ等と購入して、財布の紐は緩みます。将来の労働人口が増えて生産も消費も増えるというそんな条件の良い政策事業が子育て支援事業の他にあるでしょうか?
皇室の愛子様御誕生効果は3兆円とも5兆円とも言われております。平成12年度は出生数もわずかながら増えました。このようなお祝い事や社会的、経済的ムードの変化で出生率は変わりやすいのです。
出産祝金も相応の効果が期待できそうです。
9.政策課題
政府の経済財政諮問会議(議長=小泉純一郎首相)でも今後の社会保障制度の基本方針として次世代育成支援対策(少子化対策)の強化が盛り込まれました。マスコミもやっと少子化防止、子育て支援の必要性に気付いて高頻度に取り上げております。既に遅きに失してはおりますが、国家的緊急課題として、子育て費用の減免、扶養手当、扶養控除の増額、育児休暇、育児休職の優遇、保育施設の充実、子ども用品の免税等次々に育児支援対策を連打して、しかも長期に継続すべきです。
「子育て支援の大事さは理解されながら、具体的な施策が実行されないのは、子どもに選挙権が無いからだ」との指摘があります。誕生と同時に選挙権を与え、15歳までは親の代行を認めれば政治家は本気になって子育て支援に取り組むことになるでしょう。
10.おわりに
戦後の日本経済の復興はベビーブームによる消費の拡大とその後の労働力の増大が大きく寄与しました。
子育てには難儀苦労を伴いますが、子育てに感動し、生きる喜びを感じながら、「子育
ては楽しい」とみんなが言える社会であって欲しいと願っています。
このまま少子化が進めば日本は衰退します。世界的視野に立てば子どもの数は減ってはおりませんが、乳幼児死亡率、平均寿命などの衛生指数には格差があり、生活様式、文化、歴史は異なります。子育て支援策を充実して少子化防止に真剣に取り組み、日本の未来を明るくしてほしいものです。
日本小児科医会会報第26号(P.107〜110)に掲載されたものを転記しました。平成16年12月7日更新。
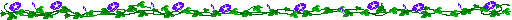
子育て支援に思う
鹿児島県小児科医会顧問 鮫島信一
わが国では、1年間に生まれる子どもの数は昭和25年230万人でしたが、その後減り続け50年後の平成12年(2000年)には
119万人と半減しました。更に50年後の2050年には60万人に半減するとの予測があります。一方老人の死亡数は減り平均寿
命が延びたことから、総人口は増え続けていましたが、昨年から減少傾向に入りました。今わが国は人類が経験したことの無い超少子
高齢社会に突入しているわけです。
長寿は歓迎できますが、少子化は国の衰退に繋がるとして、政府も「少子化防止、子育て支援」策を次々に打ち出しています。
「子は人の子、社会の宝」として認識されてはいますが、出されている「少子化防止、子育て支援策」が子どもの視点でなく、政治家
の視点、経済的視点で議論されている現状に不安を覚えます。
「子どもは遊びによって心身ともに発育する」と言われています。ある小学校の高学年に遊びについて質問したら、「遊ぶ仲間がいない。
遊ぶ時間が無い。遊ぶ場所が無い。遊び方がわからない。外は危ないから遊べない。ゲームやビデオで遊んでいる。」との答えが返って
きました。期待した遊びは、ゲームやビデオを見ることではなく、身体を動かす遊びです。汗をながし、息をはずませ、喜びに身体をふる
わせる、自然のなかの体験学習であって欲しかったのです。
ゲームやビデオは、おしゃべりも上手で退屈させませんが、作られたものであり自然ではありません。スイッチのオン・オフで
死んだ人が簡単に生き返る不自然な現象が、子どもの頃から強力にインプットされてしまいます。最近子どもの痛ましい殺傷事件が
報道されますが、犯人は「まじめでおとなしい、よい子でした」とコメントされるのが普通になっています。
少子化によって、子どもの遊び相手が、同じ年頃の子どもではなく、親であり、大人であり、祖父母であることが多くなりました。
叱るべき時に叱らず、我慢すべきと時に甘えさせ、礼儀・作法も知らないわがままな子どもが増えています。口うるさい祖父母と遊ぶより、
ゲームやビデオで過ごせば「手間のかからない、おとなしい、よい子」に評価されているのです。大人は現実の体験から、バーチャルな
世界は判別出来ますが、自然の体験のない子どもたちには、現実と区別が出来ないまま、脳裏にインプットされる危険性があります。
日本小児科学会、日本小児保健学会、日本小児科医会では乳幼児にビデオやテレビを見せないキャンペーンを行っています。
遊びの最適の場所であるはずの公園も、管理のずさんさから、各地で事故がおきています。プールの排水口管理ミスなど、あっては
ならない初歩的ミスです。幼児や学童の死亡原因の第一位が「不慮の事故」であることに注目すれば、生活環境が如何に子どもの視点
を軽視しているか指摘できます。子どもたちが元気に汗を流して遊べる環境づくりを真剣に取り組んでほしいものです。
わが国では、女性の勤務者も急速に増えてきました。働く女性にとって、出産育児と仕事の両立は難題です。しかし、子育ては親本人のた
めばかりでなく会社や社会のためでもあるとの立場から、色々な子育て支援策が登場しています。会社は労働力が欲しいので、子育て支援
に協力的になったようにみえます。しかしその方向性が誤っていると感じます。子どもが病気の時は、病児保育制が実施されています。働く
大人の視点、経済の視点から見れば望ましい制度なのですが、子どもの視点からみれば如何でしょうか? 「病気のときぐらいはお母さん
そばにいてよ」と訴えているような気がします。病児保育制を整える事も大事ですが、母親が休みたくても休めない環境を必要な時に
休める環境に変えていくことの方が重要であり急務です。
子を産みおっぱいを飲ませられるのは女性の特権です。最低3ヶ月、出来れば3歳までは母親が側で育てられれば良いのにと願っています。
その上での、育児休業制度、短時間勤務制、事業所内託児所の設置、育児休業後の職場復帰など、仕事と子育ての両立支援策は大いに歓迎出来ます。
父親の育児参加は当然ですが、子育て支援は親本人だけでなく職場全体で協力して欲しいものです。
一方、勤務している母親には、さまざまな優遇制度がありますが、子育てに専念している母親(専業主婦)には何の特典もありません。
夫の扶養控除の優遇税制も僅か30万円所得が低く算定されるだけで、名目だけの制度です。専業主婦は、「1人になれる時間が欲しい。
話す相手が欲しい。社会から取り残されるような焦りがある。子どもに何かあったら全部母親の責任といわれる。しかも経済的支援は何もない」
等と育児を荷う心身の疲れを訴えています。さらに自分の体調が悪くても、託児所や保育園に預けられないという冷遇さです。それでも、
専業主婦の多くは「子どもの心身の健やかな発育のために、幼い時こそ、側に居てやらなければ・・・・」と頑張っているのです。
子どもの視点に立てば、託児所や保育園に預けられるより、母親が側にいてくれることを望んでいます。子育ては立派な生産労働です。
子どもたちを家庭で確り育てている専業主婦に対して、積極的な子育て支援を行えば、「もっと子どもを産みたい」と考える母親が増えるでしょう。
「子育て支援、母親支援」を充実することが「少子化対策」になると確信しています。子どもが増えなけれは、明るい日本の未来は描けません。
子育てには、20年〜30年の歳月を要するので喫緊の課題です。
(さめしま小児科)
| 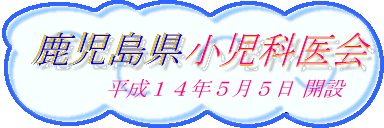
 鹿児島県小児科医会も歴史と伝統があります。
鹿児島県小児科医会も歴史と伝統があります。人目の来訪者です

 お知らせ
お知らせ ご挨拶
ご挨拶 役員名簿
役員名簿 少子化防止で日本を救おう
少子化防止で日本を救おう 子育て支援に思う
子育て支援に思う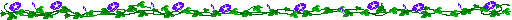
 お知らせ
お知らせ 行事予定
行事予定